子どもがお絵かきやぬりえ・工作などに集中している時やとっても楽しそうにしている時は大人だって出来るだけ続けさせてあげたいですよね。でも、どうしても時間がないときは終わらせないと・・・こんなとき、「時計の長い針がここに来たらおしまいね」と言っていてもなかなかすっと終われないことがあります。そんなときはどうしたらいいのでしょう。小さい子なら、上手く言葉でつたえられなくてかんしゃくにみえることがあります。どんな言葉を掛けてあげれば比較的穏やかにやめることができるのか、私がやってきてうまくいった方法をお伝えします。
子どもが集中している時は
まずは声を掛ける前に子どものやっていることをよく見る
時間が無いときこそ「急がば回れ」です。いきなり「さあ、時間だからおしまいね」と言うのではなく、今、子どものやっていることをよく見ましょう。
「でもそんな余裕はありません」って言葉が聞こえてきそうですが、少しの時間でいいんです。
子どもが今やっていることをよく見ましょう。
お絵かきや塗り絵なら今かいているものはあとどれくらいで出来上がりそうかな?それまで待ってあげれるかな?工作でもどれくらいで出来上がるかな?と考えて見てみましょう。もし、まだまだ続きがありそうなら、キリのいいところはどこかなと考えて、「今、おしまい と言われたらどんなふうに思うかな?」と子どもの気持ちを考えてから声を掛けていました。
では、どんなふうに声を掛ければいい?
もう少しで出来上がりそうなら「もうちょっとで終わりそうね。それが終わったらおしまいね。」と言ってあげると、たいていはすっと終われました。
それを、子どものタイミングを考えずに「さあ、時間だからおしまいね!」といってしまうと、2~3歳の子どもはまだ「もうちょっとで終わるからちょっと待って」が言えなくて癇癪を起こしてしまうことがあります。
(前にも書きましたが、かんしゃくを起こした子にはその子が何と言いたかったのか考えて、気持ちに合う言葉を掛けてあげてくださいね。そうすればやがて言葉で言えるようになってきます。)
でも、声だけ掛けて子どもにまかせていると、もっとやりたい気持ちが強いと続けて新しい絵をかき始めてしまうことがあります。すっと終われるためには終わる時を見てタイミングよく「さ、おしまいね。楽しかったね~」ともう一度声を掛けてあげると(しぶしぶでも)すっと終われることが多かったです。
そして、まだまだ続きがありそうな時は、「まだまだ描こうと思ってる?もうすぐ終わりの時間なんだけど、じゃあこの○○が描けたらおしまいにしようか?」「まだまだ●●も△△も描くの!」「そっか、●●も△△も描きたかったんだね~。・・・・・だけどもうおしまいの時間だからね、じゃあ●●が描けたらおしまいね」ときっぱり伝えてもっと描きたい気持ちに共感しながらキリのいいところで終われる提案をしてあげるのがおすすめです。
これはアニメやゲームなどの時も同じで、早めの時間に「あと10分で終わりの時間だからキリのいいところで終わるよ」などと声を掛けてあげると、盛り上がっているところで「さあ時間だからもうおしまいね」というよりずっと受け入れやすくなるでしょう。大人だってドラマの今盛り上がってるところで急に「時間だからこれでおしまい!」って言われたら嫌ですよね。子どもも同じですね。
それとともに、短時間で終わってほしいとき用に、お絵かきやぬりえの場合なら小さいめの紙やぬりえを準備しておくのもよいですね。
それでもひどいかんしゃくや、手が出る、いつも素直でないなど気になる行動が続くときは
これまで書いたように対応してみても、ひどいかんしゃくや、暴言・暴力・素直でない・極端に何事もやる気がないなど気になる行動が続くときは、特に子どもの気持ちや成長欲求が満たされていないことが考えられます。モンテッソーリ教育ではこのような行動を逸脱行動といいますが、このような時に、何か子どもの集中できるものが見つかった時は、その時だけはルールをゆるめて、食事の時間なども「ご飯できたけど食べる?今日は特別、もうちょっと後にしてもいいよ」と満足するまでやらせてあげると、気持ちや成長欲求が満たされて本来の素直さ、この子らしさを取り戻せることがあります。
もし、きょうだいがおられるなどで集中できる環境がお家で作ってあげにくいときは、お教室に来られるのも良いですよ。お教室では、やりたいことに集中できる環境が準備されています。
まとめ
子どもがおえかきやぬりえなどに集中しているときは、まずは声を掛ける前に子どものやっていることをよく見る。そして、もうすぐ終わりそうか、終わりそうならそうなら、キリがよいところで終われるように声を掛ける。まだまだ終わりそうになかったら区切りのところで終われるように導く。
それでもひどいかんしゃくや、暴言・暴力・ひどく消極的など気になる行動が続くときは集中できることが見つかったらその時だけはルールをゆるめて満足するまでさせてあげると、本来のその子らしさを取り戻せることがある。
いかがでしたか?自然とやっておられる方もおられるかもしれませんが、子どもの気持ちになって考えてみるとわかると思います。でも、1歳頃の小さいうちは大人の都合で「さあこれでおしまい」と言ってもきいてくれるので、そのずっとそのつもりでいると自我が芽生えてきたとき「何でこんなにかんしゃく起こすのかな?」ってことも出てくるかもしれません。そんなときは、「子どもの気持ちになって考えてみる」そうすると自然と掛ける言葉も違ってくるのではないでしょうか。
イヤイヤ期のかんしゃくについて、まだごらんになっていない方はこちらもごらんください。

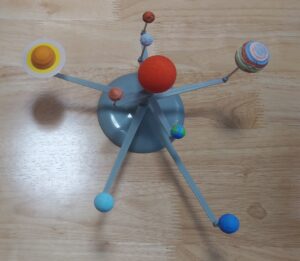


最近のコメント